部下育成を後回しにしてしまう…忙しい管理職のための脳腸メソッド
「部下育成の時間を取りたいのに、目の前の業務で手一杯…。」
「育成の重要性は分かっているが、余裕がない…。」
「教えたつもりでも、なかなか部下が成長しない…。」
多くの管理職が抱えるこの悩み。
しかし、意外なことに「時間がない」こと自体が根本原因ではありません。
部下育成が後回しになる本当の理由
「時間がないからできない」と思いがちですが、
実は 脳のリソース不足が原因になっていることが多いのです。
私たちの脳は 1日に決断できる数に限界があります。
朝から会議、資料作成、トラブル対応…
これらが積み重なった結果、脳は「決断疲れ」を起こし、
部下育成のように すぐに成果が見えない業務は後回しになってしまうのです。

「脳と腸」が育成の効率を左右する
「脳のリソース不足」が問題だとしたら、どうすれば解決できるのでしょうか?
そのカギを握るのが 腸と脳の関係(脳腸相関) です。
腸のコンディションが悪いと、
- 判断力が鈍る
- ストレス耐性が低下する
- 注意力が続かず、集中力が落ちる
つまり、腸が乱れることで脳のリソースも減り、部下育成に回す余裕がなくなるというわけです。
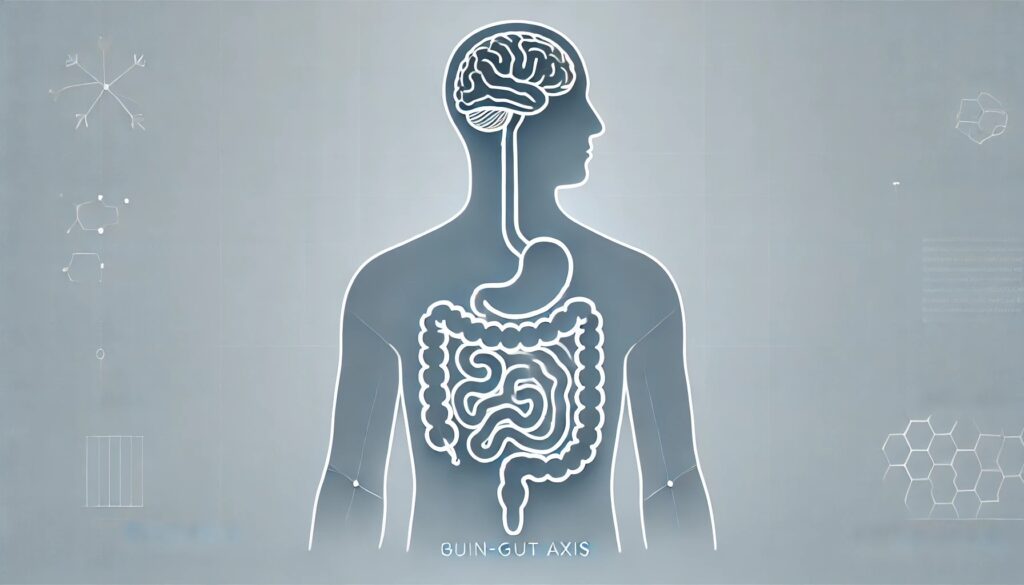
【即実践】管理職のための脳腸メソッド
ここからは、時間をかけずに「脳と腸を整え」、育成の効率を高めるメソッドを紹介します。
①「育成の決断疲れ」を防ぐ、脳のリフレッシュ法
決断疲れを防ぐには、1つの作業の後に脳をリセットする時間が必要です。
しかし、忙しい管理職には「10分の休憩を取る」余裕すらないことが多い。
そこでおすすめなのが 「マイクロパーズ法」。
やり方:
- 作業と作業の合間に 5秒だけ目を閉じる
- 意識的に 「次に何をするか」ではなく「今の思考を手放す」ことに集中する
- ゆっくり 息を3回吐き出す
たったこれだけで脳のリソースが回復し、部下育成にも意識が向けられるようになります。
② 腸から「思考のクリアさ」を取り戻す
腸内環境が悪いと、脳に炎症が起こりやすくなり、「やるべきことが分かっているのに動けない」という状態になります。
これを防ぐために、「腸の指令系統」を整えるシンプルな方法 を取り入れましょう。
おすすめは、「食事の最初に噛む回数を増やす」 こと。
具体的には、最初の3口だけ「30回噛む」 ルールを作る。
なぜなら、
- 唾液の分泌が増え、消化がスムーズになる
- 腸の負担が減り、脳のエネルギー消費が抑えられる
- 副交感神経が優位になり、ストレス耐性が上がる
これにより、頭のモヤモヤが減り、育成に集中する余裕が生まれる のです。

③ 部下が「考えて動く」ようになるフィードバックの新ルール
部下育成が負担になる理由の一つは、「指示待ち部下」に振り回されること。
しかし、これは フィードバックの与え方 によって変えられます。
多くの管理職が、「何を直せばいいか」を細かく指示しすぎる傾向があります。
その結果、部下は「考える力」を使わなくなり、常に上司の指示を待つ状態に。
この悪循環を断ち切るために、「逆質問フィードバック」を取り入れましょう。
▶ 逆質問フィードバックのやり方
- 部下の報告を受けたら、すぐに答えを言わない
- 「次に進むなら、どんな選択肢がある?」と問いかける
- 部下が考えを出したら、「その中で最も優先すべきことは?」と続ける
- 答えを導かせた後に、「なぜそれを選んだ?」と理由を聞く
こうすることで、部下は「自分で考え、決める習慣」がつき、上司の負担が減っていきます。

④ チーム全体のエネルギーを高める「腸活リーダーシップ」
管理職が疲弊すると、チーム全体のモチベーションも低下します。
実は、これも「腸の状態」が影響しています。
腸内環境が悪化すると、ストレス耐性が低下し、
・チームの雰囲気が悪くなる
・感情的な指示が増える
・冷静な判断ができなくなる
といった問題が発生します。
そこで、日々の会議や1on1で実践できる 「腸活リーダーシップ」 を試してみましょう。

▶ 腸活リーダーシップの3ステップ
- 「結論」より「プロセス」を聞く
腸が整うと、思考の柔軟性が増します。
部下の結論をジャッジするのではなく、「どう考えたか?」を聞く習慣をつけましょう。 - 「行動を褒める」ことで、腸の報酬系を刺激
人は成功体験を重ねると腸内のセロトニンが増え、前向きな思考になります。
「結果」ではなく「やったこと」そのものを評価すると、部下の成長速度が上がります。 - 「腸の働きをよくする」食習慣をチームに取り入れる
朝の軽い咀嚼習慣や、昼食時の腸に優しい食事の選択肢を共有することで、
チーム全体のストレス耐性が上がり、前向きなコミュニケーションが増えていきます。
まとめ
部下育成の時間が取れない原因は、「時間」ではなく「脳と腸のリソース不足」にある。
✅マイクロパーズ法で脳の決断疲れを防ぐ
✅「最初の3口30回噛む」で腸を整え、思考のクリアさを高める
✅「逆質問フィードバック」で部下が自ら考える力を養う
✅ 「腸活リーダーシップ」でチームのモチベーションと判断力を底上げ
これらを取り入れることで、短時間で成果を出し、部下が自走する環境を作れる ようになります。
🎁 2つの特典をプレゼント!
今だけ、無料で特典をプレゼント!
- 共通特典: 「腸が整えば、心も整う!ストレスを跳ね返す5つの簡単ステップ」
- 管理職の方向け特典: 「結果を出すチームの秘密!リーダーが避けるべき3つの落とし穴
部下育成の負担を減らし、自分もチームも成長する環境を作りませんか?

